こんにちは。ポッキーです。
この記事は、2025年の受験された吉川さん(仮名)から頂いたコンクリート診断士の合格体験記を紹介したいと思います。しかも、一発合格です。素晴らしいですね。すごいですね。
この方は、46歳のコンクリート業界の方です。前職は、工業製品の部品設計です。コンクリート業界に入って5年くらいですが勉強されて合格された方です。
これから合格体験記を紹介しますが、勉強法はさることながら気持ちの変化も感じ取れます。徐々に自信が持てるようになっていく経緯がとても心に刺さると思います。もちろん公開OKを頂いております。
それでは紹介致します。
コンクリート診断士一発合格体験記
40代で異業種からコンクリート業界へ転職し、受験時は46歳、脳も体もバリバリに衰えつつあることを自覚せざるを得ないおっさんのコンクリート診断士受験体験記です。
◆◇診断士受験の背景◇◆

大学(専攻:経済)卒業後、20代はITエンジニア、30代は地元に帰って工業製品の部品設計の仕事をしてきました。
設計自体は大好きな仕事だったのですが、帰宅は毎日日付が変わる頃で、納期に間に合わせるため徹夜・休日出勤が常態化、毎月残業時間が100~120時間で高プレッシャーな環境なため、「このままだと50歳前には死ぬな」と感じ、転職。
41歳で生コンクリート試験関係の仕事に就き、24年にコンクリート技士試験に合格。
現在の職場で出世するにはコンクリート主任技士の資格が必須なため早く取りたいが、技士登録後2年以上の実務経験が規定上必要。
ただし、診断士の資格があれば受験可能になるため、主任技士受験を1年早めるために診断士試験に挑戦。
以上の経歴ですので、生コンのJIS規格については業務上常に触れていますが、建築・土木ともに完全に素人です。
現在の職場はノー残業・ノーストレスですが、激務の前職に比べて給料は激減しました。
しかし、「命あっての物種」です。
上層部からは面談時に、今後は診断士資格保有者は現行の資格手当に加え、昇給でもさらに踏み込んで評価すると言われました。
現在の職場・業務内容・生コン業界が気にいっているため、出世と昇給に駆られての診断士受験ですが、勉強を進めていくうちにこの資格を絶対に取得し、さらにコンクリートの知識を深めたいと考えるようになりました。
◆◇診断士取得のための費用◇◆

【コンクリート工学会※必須】
eラーニング 22,000
受験費用 16,170
(受験交通費 1,650)
【学習教材】
Pockyさんのテンプレ 6,200
【問題集】
『コンクリート診断士 2025年版』 (建築資料研究社) 4,950
『コンクリート診断士試験 完全攻略問題集 2025年版』 (コンクリート新聞社) 4,950
『2025年版 コンクリート診断士試験 合格指南』 (日経BP) 4,180
【勉強会】
コンクリート診断士受験対策講座2025(東海診断士会) 6,000
(対策講座交通費 1,500)
合計 67,600
交通費を除いたら、取得にかかった費用は約6万5千円でした。
◆◇勉強時間◇◆

3月から開始し、1日平均にならすと約3時間程度勉強していました。
約150日×3時間 = 450時間
※3月は勉強の方向性が定まらず、あまり身が入らなかったため、今から思うと本当にもったいない時間の使い方をしていました。
平日は仕事のスキマ時間(基本的に依頼者が来たら試験を行う仕事なので、待ち時間が存在する)や昼休み、帰宅後の時間を使って1日3時間程度を充てました。
5月までは土日祝日は家族サービスや自宅の庭整備などにかまけて、勉強は早朝の30分程度しかできていませんでした。
6月からは流石にまずいと思い、休日は朝から夕方まで勉強していました。
毎日、朝晩の犬の散歩時にyoutubeの1問1答動画をずっと聞き流していました(これは勉強時間に含めず)。
◆◇勉強順序◇◆

1.知識の習得 3月~4月(本当は年明けから始められたら最高)
2.四択対策 4月~7月中旬(問題集3冊を3~5周)
3.論文対策 6月~7月中旬(診断士会の対策講座受講直後から)
4.本番想定 7月中旬~試験日前日
後述のように焦り始めてから一気に勉強を加速したので、かなりスケジュールに無理がありました。
今思い出しても、しんどすぎました。
1月にPockyさんの「【難易度A】すごい資格 コンクリート診断士を戦略的に勉強」(https://yumonaoirokona.com/concrete-diagnostician/how-to-study/)を読んでいれば、もっと無理なく勉強を進められたのに。。。
後悔先に立たずです。
◆◇知識の習得◇◆

4月からeラーニングを開始し、テキスト『コンクリート診断技術』を読み始めるも、内容は全く頭に入りません。
このままではとても合格はおぼつかないと焦りを覚え、診断士試験対策の情報をネット上で真剣に探し始めました。
Pockyさんの「【難易度A】すごい資格 コンクリート診断士を戦略的に勉強」(https://yumonaoirokona.com/concrete-diagnostician/how-to-study/)を読み、”必要な勉強法はこれだ!!”と腑に落ち、Pocky さんの他の記事も読み進めて内容を理解し、記述式テンプレートを購入。
ブログに書かれている通り、劣化のメカニズム、特徴、劣化過程、調査方法、補修・補強方法を理解してから、下記で紹介するシノダレジュメや、問題集の解説を読むとこれまでとは全く違う体系的な知識を得られる手ごたえを感じはじめ、ようやくエンジンがかかりました。
PockyさんのブログやシノダレジュメをExcelに書き出してまとめ、それを印刷して、さらに調べる必要があるところを『診断技術』やネットで調べて書き加え、自分なりのテキストに仕立てました。
Pockyさんの変状ごとの記事に加え、必須75問が体系化を行う上で大変有効で、よく活用させて頂きました。
診断士会の対策講座を受講する前に知識を体系化できていたため、講座は劣化機構の復習として大変有用でした。
6月に行われた東海診断士会が行っている対策講座は、診断士試験の概要・論文作法にはじまり、主要な劣化機構の解説まで、至れり尽くせりてんこ盛りな内容で大変勉強になりました。
現在バリバリに診断士として活動している方々から、勉強方法や考え方を直接聞けたのは本当に貴重な体験でした。
診断士会の講座テキストからも必要箇所を追加したことで、自分なりのオリジナルテキストが完成しました。
変状ごとにメカニズム、特徴、劣化過程、調査方法、補修・補強方法を、自分なりに体系的にまとめる作業は膨大な時間がかかりますが、「急がば回れ」の特に重要なプロセスだと思います。
◆◇四択対策◇◆

下記3冊を購入し、繰り返し解きました。
青の蛍光マーカーで正解番号を塗りつぶし、赤透明の下敷きで隠して答えを見えなくしました。
試験直前2週間前までは問題集の本文には一切書き込みを行わず、繰り返し解きました。
正答・誤答をExcelで一覧表を作って入力し、間違った問題と正答率を把握しながら進めました。
直前2週間前からは、問題文にアンダーラインを引いたり、キーワードを丸で囲む、選択肢を消し込むなど、本番で効率よく回答する手順を確認しながら解きました。
後述のように、試験では27/40(67.5%)しか正答できませんでした。
勉強方法は大いに再考の余地があるようです。
全ての選択肢と深く向き合い、正解・不正解の理由を明確に述べる事ができるまで覚え込まないといけないと感じています。
何となく感覚で選択肢を消去して正解したまま放置していた知識が多すぎたようにも思います。
●『2025年版 コンクリート診断士試験 合格指南』(日経BP)
四択問題については要点を抑えた問題を取り上げ、丁寧に解説してあるので、学習初期に解説をよく読んでいました。
●『コンクリート診断士 2025年版 』(建築資料研究社)
四択過去問を分野別に735問掲載+記述式全過去問掲載。
問題数が多く、その分解説は少なめ。
分野別になっているのは、大変有難かった。
ポイントをかいつまんだシノダレジュメもあり。
勉強を始めた当初、シノダレジュメを読んでも、何が書いてあるのかさっぱりわかりませんでした(笑)。
Pockyさんの様々な解説記事を読んで理解したあと、もう一度読み返したら簡にして要を得たレジュメだと理解でき、何度も読み返すようになりました。
この問題集を5周し、5回とも正答した問題は消し込み、それ以降は1回でも誤答した問題をひたすら解きました。
●『コンクリート診断士試験 完全攻略問題集 2025年版』(コンクリート新聞社)
直近5年分の全問題と解答・解説+オリジナル問題100問を掲載。
過去問、オリジナル問題ともに解説がとても丁寧。
オリジナル問題を3周しました。
その後、過去問直近5年分を5周しました。
最初のうちは正答・誤答問わず、解説を丁寧に読んで理解しながら進めました。
5回目にはすべての問題に正答できるようになりました。
◆◇記述対策◇◆

Pockyさんの有料テンプレートを購入し、テンプレートを頭に入れました。
これによってどんな問われ方をしても、それなりの解答が出来るのではないかと思え、背骨が一本通ったような気がします。
地域の診断士会が行っている記述問題対策講座に参加し、論文作法や試験当日の時間配分、問題文の精査の仕方、設問ごとの文字数の割り振り方、下書きの作成方法などを具体的に学ぶことができました。
実際に講師が合格した時の試験中に問題用紙に書いた下書きを見せて頂いたり、3回目でようやく受かったなどの苦労話も伺えました。
記述も四択と同じ問題集3冊を使いました。
3冊の解答例は記述方法も、場合によっては変状の推定結果も様々ながら、共通していたのは問題文の中にある根拠に基づいて、説得力のある記述がなされているという点だと思いました。
しかし、納得がいく部分と?と思う部分がそれぞれの解答例にあり、帯に短したすきに長しと感じました(プロに対して生意気すぎ)。
プロの解答例でもこれだけ記述方法も解答内容も違いが出てくるということは、本番の採点もかなり幅があるに違いないと思いました。
そこで、下記2点を意識して自分なりに3冊の解答例をいいとこ取りしたり、自分でこれは絶対に必要だと思う部分を追加したりして、自分なりに納得できる解答を作成しました。
・Pockyさんの有料テンプレートの記述の順序や文章のテンポの良さを意識する
・診断士会で教えてもらった、設問に対して忠実に順番通り解答することを意識する
解答作成を行う前に、劣化機構ごとの特徴、劣化等級、調査方法、補修・補強方法をリスト化したものを暗記していて、問題に応じて組合せて答えられるようになっている事が重要だと思います。
リストが頭に入っていれば、一発NGな解答を作成してしまう事は無いと考えました。
解答作成練習は、本番の記述用原稿用紙と同じように1枚が25文字×20行のものをネットから印刷し、設問内容に応じて文字数を割り振りながら行いました。
診断士会の対策講座の中でも、「近年は一つの問の中でも多数の事柄が問われるため、場合によっては問1だけで500文字程度になってしまう場合もありうる。全ての問を読んだうえで、どの問にどれくらいの文字数を割り振る必要があるのか把握することが必要」といった趣旨の話がありました。
解答の最後数行に記述する点検強化や予防保全の文章も、残り行数に応じて2~4行で書けるように複数用意し、問題に応じて柔軟に変えるように心がけました。
6月下旬に試験当日に使うシャーペン/電卓/時計を調達し、普段から使って慣れるようにしました。
電卓は四則+√機能(過去問では√を計算する問題あり)があり小型のものを選択しましたが、小型すぎて使いづらかった点は後悔しました。
シャーペンは長時間書いても疲れにくいように、実際に店舗で試し書きして自分にあったものを選びました。
普段腕時計をする習慣がないため試験用にチープカシオを購入し、過去問を解きながら経過時間を測り、時間を配分しながら問題を解く癖をつけていきました。
◆◇本番の時間配分を検討◇◆
普段はほぼ100%PCで文書作成を行っており、若い頃からプレゼン資料や記録文書、マニュアルを大量に作ってきたため、構成を考えて書くことには全く抵抗はありません。
しかし、手書きでは人並みはずれた悪筆な上に、文字を書くのが非常に遅いという致命的な欠点があります。
“読める文字を書く”という作業に苦戦する事がわかりきっているため、“せめて丁寧に書く“時間を捻出することに重点を置かなければ、合格できないと考えました。
【最善】
択一:40問を60分で解く(1問1.5分 = 10問15分を目安)
記述:①問題文と写真・図表の理解、下書きに30分 ②記述に80分 ③見直し10分
【通常】択一に苦戦した場合を想定
択一:40問を90分で解く
記述:①問題文と写真・図表の理解、下書きに30分 ②記述に60分
◆◇試験本番◇◆

択一は過去問より初見の問題が多い印象を受けたが、テンポを乱すことなく解き進んだ。
10問で15分のペースを心がけ、事前想定通り60分で解き終わり、残り2時間を記述に充てた。
記述の建築は新パターンの疲労のため秒で諦め(笑)、覚悟を決めて土木の問題を解き始める。
当初の予定通り30分でネタ集め・文章の下書きを問題空白に書き終え、80分を目途に書き終わることを想定して書き始める。
試験終了15分前にはどうにか書き終えたが、我ながら大変な悪筆なため、読みにくいと思う字を消して書き直すを繰り返した。
論文は一度最後まで書き終えてしまうと、見直しの10分で修正できるのは文字の書き直し程度で、途中の文章はほぼ修正不可能です。
設問に合わせてポッキーさんのテンプレートの結論→理由→具体例の順序を下書き段階から崩さずに推敲していく事で、文章の修正なく書き切ることにつながると思います。
◆◇解答速報で答え合わせ◇◆
翌朝に解答速報で採点し、択一 27/40 (67.5%)
もっと正答できたと思っていたため、現実との巨大なギャップを認識し、1日中打ちひしがれていました。
それなりに過去問をやり込んだと思っていたため、これだけしか正答できなかったのは本当に悔しいです。
また、本番の緊張・焦燥からなのか、後から考えれば「その選択肢は絶対に無い」とわかる不正解を選んでしまった問題が3問ありました。
Pockyさんのブログにも心がけとして“全力で満点を取りにいく“ことの必要性や、他のネット上の体験記でも“満点を取りにいってようやく足切りを逃れられる“といったことが書いてありました。
「これだけ勉強したから大丈夫」と高をくくっていましたが、本当にその通りになってしまいました。
四択がこれだけしか正答できなかったことに対して、自分の中ではまだ明確な結論が出ていません。
今後、主任技士・技術士を受けるにあたり、勉強方法をよく検討する必要があります。
記述の答え合わせはPockyさんの解答例にて確認。
解答例のように上手にはまとめられなかったうえに、第三者被害防止を書き逃しました。
論文の出来の良し悪しはともかくとして、後から論文を再現することが全く頭から抜けていたのは、痛恨のミスでした。
勉強時はつねに手元に練習した論文が残っているためすぐに読み返せますが、本番後に再現するには「再現するんだ」と意識して書き、試験後すぐにカフェにでも入って再現しないと難しいと感じました。
試験会場を後にしたその足で、一緒に受験した知人と焼き鳥屋で反省会を行ったら、開放感とともに記述内容もパァーッと飛んでいってしまいました(笑)。
今後、主任技士や技術士を受験する際は、試験後に論文の再現を正確に出来るようにしなければならないと猛省しています。
まとめ

吉川さん(仮名)の一発合格体験記、とても臨場感があって受験生の心に響く内容になっていますね。特に「異業種から挑戦」「40代での再スタート」「勉強時間や費用を具体的に記録」「テンプレート活用で自信を持てた」という点は、これから受験する方に強い共感と安心感を与えると思います。
よかったら、覗いてみて下さい。👇
【2026年版】記述式が苦手でも合格できる!220人が使ったコンクリート診断士テンプレート
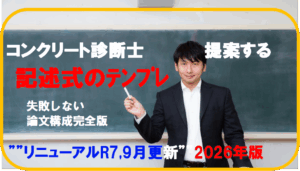

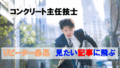
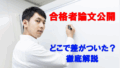
コメント