こんにちは。ポッキーです。
コンクリート診断士試験の記述式問題、苦戦していませんか?
「知識はあるのに、どう書けば点が取れるのか分からない…」
そんな悩みを抱えている方は多いと思います。
今回ご紹介するのは、実際にこの有料記事を購入し、見事に合格された3人のリアルな体験談です。
「4回目の受験でようやく合格」「初受験で一発突破」「10年ぶりの挑戦でリベンジ成功」―― それぞれの背景は違いますが、共通していたのは「記述式の書き方が分からなかった」ということ。
しかし、この記事のテンプレートを活用し、論理的な論文の書き方を身につけたことで、合格を勝ち取ることができました。実際にどのように活用し、どう合格につながったのか?そのリアルな声をお届けします。この度ご協力して頂いた3名仮名(田中さん、佐藤さん、中村さん)の方には大変感謝申し上げます。
これから受験する方は、ぜひ参考にしてください!
「4回目の挑戦でついに合格!この記事が突破口になった理由」
4回目の受験で合格した方のプロフィール
名前(仮):田中さん

年齢:37歳
職業:建設会社の技術者(中堅社員・課長補佐)
経験年数:15年
勤務先:ゼネコンの橋梁保全部門
受験の動機:会社の昇進要件としてコンクリート診断士の取得が必須だったため
受験までの経緯
- 1回目(34歳):筆記試験は合格したが、記述式で基準点に届かず不合格。
- 2回目(35歳):記述式対策として過去問をひたすら書いたが、論理が弱くまた不合格。
- 3回目(36歳):独学で論文対策を強化したが、書き方の軸が定まらず、わずかに基準点に届かず不合格。
- 4回目(37歳):「これが最後のチャンス」と考え、確実に合格するために論文対策の教材を探していたところ、ブログの記事を見つけ、有料記事を購入。
私は、コンクリート診断士試験に3度挑戦し、不合格を経験しました。特に記述式問題が最大の壁で、過去3回とも基準点を超えることができずに悩んでいました。専門知識はある程度身についているはずなのに、論文の書き方が分からず、何をどう書けば得点につながるのかが全く見えてこなかったのです。
そんなときに出会ったのが、この**「記述式のテンプレート記事」でした。最初は半信半疑でしたが、試験本番で使える「書き方の型」が学べるという点に惹かれ、思い切って購入。結果的に、このテンプレートが合格の決め手**となりました。
この記事の活用法と効果
✅ 論文の型を覚えることで、スラスラ書けるようになった!
これまでは、記述式の解答を書くたびに「どこから書き始めればいいのか?」と悩んでいました。でも、このテンプレートでは「結論 → 理由 → 具体例」という構成がしっかり示されていて、迷わず書き始めることができました。
✅ キーワード整理の重要性を知り、的確に論じられるように!
記事では、問題文から必要な情報を整理する方法が詳しく解説されていました。実際に本番の試験でも、記事で学んだように「設計条件」「現場条件」といったキーワードを抜き出し、それに沿って論述することで、一貫性のある解答を作ることができました。
✅ 「記述の説得力」を上げるコツが詰まっていた!
ただ知識を書くだけではなく、「なぜその調査が必要なのか?」や「この補修工法を選んだ理由」まで明確にすることが重要だと学びました。その結果、これまで曖昧だった記述が、試験官に伝わる論文へとレベルアップ。
結果:4回目の試験でついに合格!
この記事を活用したことで、記述式問題の解答が「何となく書く」から「論理的に説明する」へと大きく変わりました。これまで苦手だった記述式で基準点を超え、ついに合格。
もし、過去の私のように「記述式が苦手で合格できない」と悩んでいるなら、このテンプレート記事を強くおすすめします。合格するために「何を書くべきか」が明確になり、得点につながる論述ができるようになるはずです!
「1回の受験で合格!このテンプレートがあったからこそ突破できた」
【1回で合格した受験者のプロフィール】
名前(仮):佐藤 さん

年齢:28歳
職業:橋梁設計エンジニア
経験年数:6年
勤務先:建設コンサルタント会社(設計部門)
受験の動機:設計業務において劣化診断の知識を深めるため
受験までの経緯
- 初めての受験(28歳):
・筆記試験対策は順調だったが、記述式論文の対策に不安を感じる。
・仕事で論文を書く機会がなく、「何をどう書けばいいのか分からない」状態。
・過去問を見ても、論述のポイントがつかめず、独学での対策に限界を感じる。
・試験前に記述式の型を学ぶため、有料記事を購入。
私は28歳の橋梁設計エンジニアとして働いており、コンクリート診断士試験に初めて挑戦しました。設計業務には慣れていましたが、記述式論文の試験はこれまで経験がなく、「どのように書けば合格できるのか」まったく見当がつかない状態でした。
試験勉強を進める中で、過去の受験者の話を聞くと、「記述式が難しくて何年も不合格を繰り返している人が多い」とのこと。そこで、最初の受験で確実に合格するために、効率的に学べる教材を探していたところ、このテンプレート記事を見つけました。
記事を活用した結果…
✅ 「何を書けばいいのか」が明確になった!
これまで論文を書いた経験がなく、「どこから手をつければいいのか?」と悩んでいましたが、この記事では「論文の基本構成」が明確に示されていました。特に「結論 → 理由 → 具体例」の流れが分かりやすく、テンプレートに沿って記述するだけで、論理的な文章が自然と書けるようになりました。
✅ 試験本番で焦らなかった!
試験中、時間配分を誤ることなく、スムーズに論述が進みました。なぜなら、事前にこの記事のテンプレートで何度も練習し、どのように展開すればよいかを身につけていたからです。「要点を簡潔にまとめるコツ」も記事に書かれており、限られた時間内で効果的な記述ができました。
✅ 記述式で高得点を獲得し、1回で合格!
試験後に自己採点をしたとき、記述式の解答が「的確に書けた」と感じました。結果、1回の受験で見事合格! 先輩たちが苦戦している記述式を、効率よく攻略できたのはこの記事のおかげです。
これから受験する方へ
「記述式の書き方が分からない」と感じているなら、このテンプレート記事を強くおすすめします。私は独学でしたが、この記事があったおかげで記述式の対策に無駄な時間を使わず、効率的に合格することができました。記述式の「型」を学ぶことが、合格への最短ルートです!
「10年ぶりの受験で合格!ブランクを埋めてくれたのはこの記事だった」
【10年ぶりの受験で合格した受験者のプロフィール】
名前(仮):中村 さん

年齢:48歳
職業:施工管理技術者(主任クラス)
経験年数:25年
勤務先:地方ゼネコンの土木部門(維持管理担当)
受験の動機:管理職への昇進に必要だったため
受験までの経緯
-
1回目・2回目の受験(40歳):
・業務経験は豊富だったが、記述式問題の書き方が分からず不合格。
・「知識を書き並べるだけではダメ」ということは分かったが、具体的な書き方が分からないまま挫折。
・業務多忙により、その後10年間受験を見送る。 -
10年ぶりの受験(48歳):
・試験傾向が変わり、記述式対策をどうすればいいのか分からなくなっていた。
・過去問を解こうとするも、論述の流れがつかめず、ブランクの大きさを実感。
・効率よく勉強するため、有料記事を購入し、テンプレートを活用。
・「論文の型」を学ぶことで記述がスムーズになり、ついに10年ぶりの挑戦で合格!私は48歳の施工管理技術者です。20代からコンクリート構造物の維持管理に携わっており、40歳のときにコンクリート診断士試験を受験しました。しかし、2回挑戦するも不合格。当時は仕事が忙しく、「また来年受けよう」と思いながら、気がつけば10年が経過していました。
「そろそろ資格を取得してキャリアアップしないと…」と思い、再び受験を決意しましたが、10年のブランクは想像以上に大きく、特に記述式問題の解答方法を完全に忘れていました。試験問題の傾向も変わっているようで、「今さら独学で間に合うのか?」と不安になっていたときに出会ったのが、この記事でした。
この記事でブランクを埋められた!
✅ 「今の試験傾向」が分かった!
記事には、最新の試験の出題傾向を踏まえた記述式の解答ポイントが整理されていました。10年前の試験とは異なり、「どこが重点的に問われるのか?」が分かりやすく解説されており、最短ルートで対策を進めることができました。✅ 「論文の型」を覚え、書き方が身についた!
記述式は、何を書くべきか整理しないと時間が足りなくなると分かっていました。しかし、この記事には「論理的に書くためのテンプレート」があり、それに沿って練習するだけで、記述の流れが自然と身につきました。10年前にはなかった「問題文からキーワードを整理する方法」も解説されており、試験本番でも焦らずに解答を作成できました。✅ 合格に必要な「合格論文の視点」が分かった!
過去の受験では、「とにかく知識を書けばいい」と思い、要点を押さえられずに不合格でした。しかし、この記事では「採点者が何を求めているのか?」が詳しく解説されており、評価される論文を書くコツがつかめました。結果、今回は記述式でしっかり得点を獲得し、10年ぶりの挑戦でついに合格!これから受験する方へ
10年ぶりの受験で不安だらけでしたが、この記事のおかげで短期間で記述式の対策を進めることができました。 長いブランクがあっても、試験に必要な論述力を効率よく取り戻せるので、過去に不合格だった方や、久しぶりに再挑戦する方には特におすすめです!
まとめ
合格者のリアルな声はいかがでしたか。紹介している記事は、私が2022年に作成し3年になります。この間本当に多くの方に購入頂きました。この中でこのような声を頂いて本当に感謝すると共に、嬉しく思っています。皆さんの役に立っている事を実感しより一層よい記事を提供していこうと考えています。よかったらこの紹介している記事のリンクを貼っておきますので、ご興味をお持ちの方は、ぜひご覧ください。👇


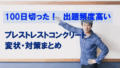
コメント