II. 施工・各種コンクリート(15問)
Q11. コールドジョイントの定義として最も適切なものはどれか。
A. すでに打ち込まれたコンクリートの凝結がすすみ、その上に新たにコンクリートを打ち重ねる場合に一体とならない継目のこと。
B. 鉄筋等でスクリーニングされて締固めが不十分なときに発生する、粗骨材が多く集まった空隙の多い箇所。
C. セメントの水和熱に起因し、部材内の温度差や外部拘束応力によって生じるひび割れ。
D. ブリーディングによる水の上昇に伴い、沈下が拘束されて発生するひび割れ。
Q12. 暑中コンクリート(日平均気温25℃を超える時期)の施工において、練り混ぜ開始から打ち込み終了までの時間として標準とされるものは何か。
A. 1.5時間以内。
B. 2.0時間以内。
C. 90分から120分以内。
D. 2.5時間以内。
Q13. 寒中コンクリートの材料加熱に関する規定として正しいものはどれか。
A. 加熱したセメントを使用すると急結を起こすリスクがあるため、セメントの加熱は禁止されている。
B. セメントは品質低下を防ぐため、50℃以下であれば加熱して使用してもよい。
C. 骨材は直火で加熱してはならないが、水は40℃を超えてもよい。
D. 強度発現を促進するため、早強ポルトランドセメントの使用は禁止されている。
Q14. マスコンクリートの温度ひび割れ対策として、水和熱低減の観点から使用が推奨されるセメントの種類として正しいものはどれか。
A. 低熱ポルトランドセメント、中庸熱ポルトランドセメント、高炉セメント、フライアッシュセメント。
B. 普通ポルトランドセメントおよび早強ポルトランドセメント。
C. 超早強ポルトランドセメントおよび耐硫酸塩ポルトランドセメント。
D. シリカセメントおよび低アルカリポルトランドセメント。
Q15. コンクリートの打込み作業における、1層の高さとして標準とされるものはどれか。
A. 40~50cm以下。
B. 30cm以下。
C. 60cm以下。
D. 80cm以下。
Q16. 棒状バイブレータを用いたコンクリートの締固めにおいて、上下層を一体化させるために下層のコンクリート中に挿入する深さの目安はどれくらいか。
A. 10cm程度。
B. 5cm程度。
C. 20cm程度。
D. 30cm程度。
Q17. コンクリートの再振動を行う際の実施時期に関する標準的な目安として正しいものはどれか。
A. 打終わりから15分~60分程度で、練り混ぜ開始から120分以内(気温が25℃を超える場合は90分以内)。
B. 練り混ぜ開始から180分以内であれば、打終わり時間に関わらずいつでもよい。
C. 打終わりから6時間以内、かつ、練り混ぜ開始から240分以内。
D. 打終わりから120分以降で、凝結終結時間までに行う。
Q18. 高流動コンクリートの特徴に関する記述として、最も適切なものはどれか。
A. 締固め不要の自己充填性を有し、複雑な形状や過密配筋の構造物にも密実に充填できる。
B. 締固めが必要であるが、流動性が高いため型枠側圧は普通コンクリートより低下する。
C. 締固めは必須であるが、ポンプ圧送時の管内圧力損失は普通コンクリートよりも小さい。
D. 単位水量が少なく設計されるため、自己収縮ひずみは普通コンクリートよりも小さい。
Q19. 高流動コンクリートは、分離抵抗性を付与する方法により、主に3つの系統に大別される。その分類として正しいものはどれか。
A. 粉体系、増粘剤系、併用系。
B. 高強度系、早強系、低発熱系。
C. 低収縮系、再生材系、環境貢献系。
D. 水中不分離系、繊維補強系、自己治癒系。
Q20. 水中不分離性コンクリートの施工上の留意点として、水中落下高さの制限はどの程度か。 A. 50cm以下。
B. 1.0m以下。
C. 1.5m以下。
D. 2.0m以下。
Q21. 流動化コンクリートに関する記述として、圧縮強度に関する事項で正しいものはどれか。 A. 圧縮強度は、通常のコンクリートと変わらない。
B. 流動化剤の作用により、通常コンクリートよりも圧縮強度が10%以上増大する。
C. 流動化により単位セメント量が増加するため、圧縮強度が大幅に向上する。
D. スランプが増大するため、通常コンクリートよりも圧縮強度が低下する。
Q22. 舗装コンクリートの品質管理において、特に重要視され、管理指標として用いられる強度として正しいものはどれか。
A. 曲げ強度(4.5N/mm²)で管理する。
B. 圧縮強度(50N/mm²)で管理する。
C. 引張強度(3.0N/mm²)で管理する。
D. 支圧強度で管理する。
Q23. 鉄筋コンクリート構造物の施工において、かぶり厚を確保するためにスペーサーを配置する際の目安として、側面の配置はどの程度が目安となるか。
A. 2個/m²以上。
B. 1個/m²以上。
C. 3個/m²以上。
D. 4個/m²以上。
Q24. コールドジョイントが鉄筋コンクリート構造物に発生した場合に懸念される最も大きな影響は何か。
A. コールドジョイントを通じてコンクリート中の鋼材の腐食を増進させることが懸念される。 B. 部材内の温度差に伴う内部拘束応力を増加させ、初期ひび割れが拡大する。
C. コンクリートの凝結が遅延し、所定の強度発現が困難となる。
D. トンネルライニングに発生した場合と同様に、剥離による第三者障害に直結する。
Q25. 高流動コンクリートの施工における、型枠に作用する側圧の計算上の留意点として正しいものはどれか。
A. 安全サイドの配慮から、コンクリート全体を液圧として考慮する必要がある。
B. 流動性が高いため、側圧は普通コンクリートの1/2として計算できる。
C. 塑性粘度が高いため、側圧は普通コンクリートと同等としてよい。
D. 自己充填性があるため、静的な水圧として計算するが、打上がり速度の影響は無視できる。
III. 維持管理・耐久性・試験(10問)
Q26. コンクリートの中性化の進行を表す式として正しいものはどれか。
A. X=b√t (b:中性化速度係数、t:時間)。
B. X=b/t
C. X=b/t2
D. X=bt2
Q27. コンクリートの塩害対策として有効な方法として正しいものはどれか。
A. 水セメント比を小さくする(コンクリートの組織を緻密化し、塩化物イオンの侵入を抑制する)。
B. 単位セメント量を減らし、中庸熱セメントを使用する。
C. 単位水量を増加させ、ワーカビリティーを向上させる。
D. 粗骨材の最大寸法を大きくし、鉄筋の最小あきを広くする。
Q28. 海洋コンクリート構造物において、海水の作用と酸素供給が積極的に行われるため、最も鉄筋腐食を受けやすい部位はどこか。
A. 干満帯や飛沫帯。
B. 常時海面下にある部分(海中帯)。
C. 海面より十分に高い位置にある部分(大気中)。
D. 海底の地盤面下にある部分。
Q29. コンクリートの強度推定に用いられる非破壊試験方法の一つ、反発度法(シュミットハンマー)の短所として最も適切なものはどれか。
A. コンクリート表面の状態に測定値が大きく影響を受ける。
B. 局部的に破壊するため、構造物の健全性を損なう。
C. 波の干渉により測定が困難になることがある。
D. 放射線防護のための安全管理が必要となる。
Q30. ひび割れ発生時に発生し伝播する弾性波を検出する方法で、リアルタイムにひび割れを検出できる非破壊試験方法は何か。
A. アコースティック・エミッション(AE)法。
B. 自然電位法。
C. 電磁波レーダ法。
D. 赤外線法。
Q31. コンクリートの中性化深さの測定に一般的に用いられる試薬はどれか。
A. 1%濃度のフェノールフタレイン溶液。
B. 塩化銀溶液。
C. チオシアン酸アンモニウム溶液。
D. 炭酸カルシウム飽和水溶液。
Q32. コンクリートの耐凍害性を評価する凍結融解試験(JIS A 1148)において、評価指標として測定されるものは何か。
A. 相対動弾性係数(および耐久性指数、質量減少率)。
B. 圧縮強度。
C. ポアソン比。
D. クリ―プ係数。
Q33. コンクリート構造物の維持管理手順のうち、日常点検では発見しづらい劣化や損傷を調査するために行う「定期点検」の一般的な間隔はどれくらいか。
A. 5年や10年など比較的長期の間隔。
B. 1年に1回以上。
C. 異常事態が発生した時点。
D. 30年ごとに一度。
Q34. 硬化コンクリートの強度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
A. 圧縮強度は、他の強度(引張強度、曲げ強度、せん断強度)の推定に利用される最も代表的な強度であり、他の強度に比べて最も大きな値を示す。
B. 圧縮強度は、疲労限度(200万回疲労強度)の約55~65%である。
C. せん断強度は圧縮強度と引張強度の和に比例して決まる。
D. 引張強度は、圧縮強度に比べて著しく大きく、設計に主に用いられる。
Q35. 温度ひび割れや乾燥収縮ひび割れの発生が予想される場合の設計上の対策として有効なものは何か。
A. 用心鉄筋でひび割れ幅を小さくする方法や、ひび割れ誘発目地を用いて発生位置を制限する方法。
B. 単位セメント量を大きくし、水和熱を増大させる。
C. プレキャスト型枠の使用を避け、打設時の拘束力を最大化する。
D. 高性能AE減水剤を使用せず、ブリーディングを促進させる。
IV. 配合・品質管理・その他(5問)
Q36. JIS A 5308に規定される、舗装コンクリートのスランプの規格値として正しいものはどれか。
A. 2.5 cm, 6.5 cm。
B. 8 cm, 12 cm, 15 cm。
C. 18 cm, 21 cm。
D. 50 cm, 60 cm。
Q37. コンクリート構造物の品質保証における性能規定の特徴に関する記述として、正しいものはどれか。
A. 設定した構造物の挙動を予測し、その結果が要求目的を満足することを定量的に客観的に示すためのものであり、設計・施工方法が限定されず自由度が高い。
B. 構造物全体の挙動ではなく、個々の断面チェックを主な検討対象とする。
C. 性能(結果)ではなく、材料選定や配合といったプロセス(仕様)の遵守を重視する。
D. マニュアルに従い、技術者の経験や応用力を排除することを基本とする。
Q38. レディーミクストコンクリートの受入れ検査において、検査項目の一例として挙げられているものは何か。
A. 強度、スランプ、空気量、塩化物含有量など。
B. 絶乾密度、粗粒率、吸水率、および膨張率。
C. 圧縮クリープひずみ、熱膨張係数、および動弾性係数。
D. 骨材のアルカリシリカ反応性、セメントの安定性、および未燃焼カーボン量。
Q39. JIS A 6204に規定される高性能AE減水剤以外の混和剤(流動化剤など)を用いて流動化コンクリートを製造する場合、流動化後15分後のスランプの経時変化量の上限値はどれくらいか。
A. 4.0 cm以下。
B. 1.0 cm以下。
C. 2.0 cm以下。
D. 5.0 cm以下。
Q40. コンクリート構造物の現場施工における生産性向上策の一つとして、構造物形状の単純化が提案されている。この単純化のために材料費が増加したとしても、ある一定規模以下の構造物であればコスト的に有利となる根拠は何か。
A. 労務費の削減。
B. プレキャスト化による運搬費用の低減。
C. 高流動コンクリートの使用による型枠費用の低減。
D. 単位水量の削減によるコンクリート単価の低減。


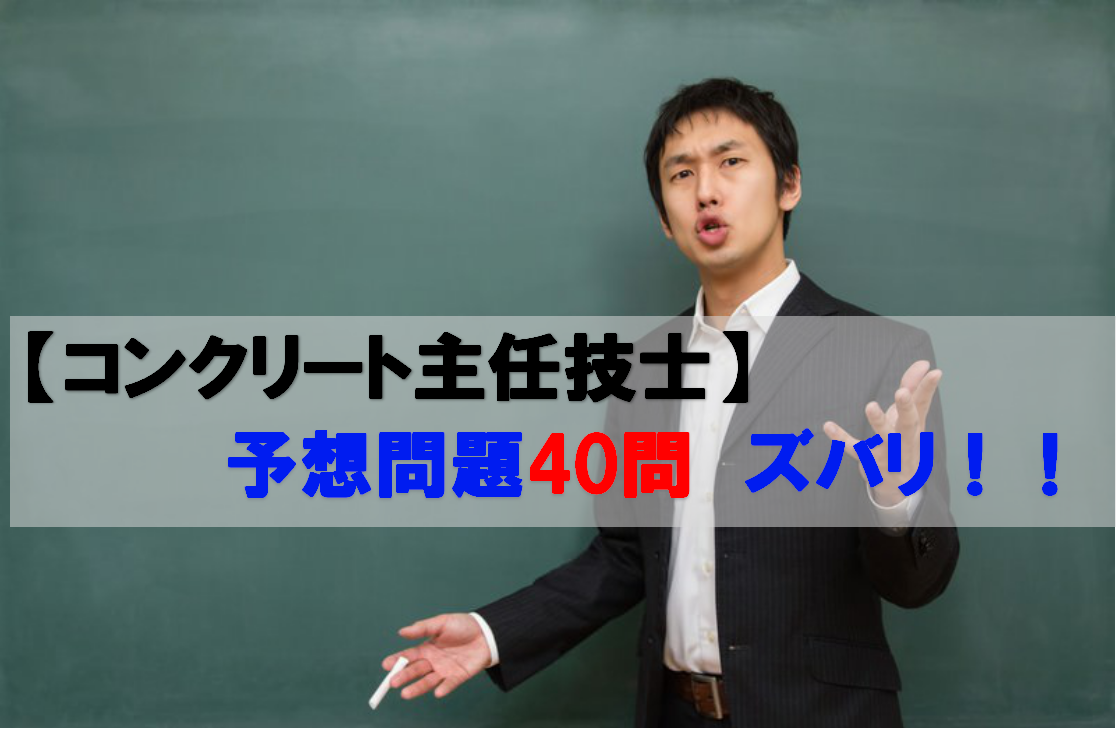
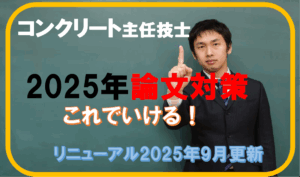


コメント