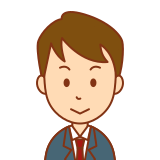
こんにちは。ポッキーです。
本日の記事は、受験者の皆さんが特に気になること間違いなしです。自信を持って公開いたします。
それは、2025年に行われたコンクリート診断士合格者の2名(40代、50代、お二人とも27/40(67.5%)の四択正解率)の方が再現論文を提供して頂きましたので公開したいと思います。もちろん、当ブログ記事をご活用して頂いたお二人になります。※もちろん掲載の承認は頂いています。
また、それに併せて”私”が「この論文がなぜ合格論文なのか」を紐解いてみたと思います。どこが良かったのか次の8項目を基本に具体的に解説していきたいと思います。

① 問題文の意図に正面から答えている
② 数値や試験結果を根拠に使えている
③ 劣化の進行予測が現実的
④ 対策が現場レベルで具体的
⑤ 論理の流れが一貫している
⑦ 再劣化や維持管理への視点がある
⑧ 冗長すぎず、読みやすい分量
25年診断士試験再現論文(1人目)
問1
本橋台は約50年供用しており、東北地方山間部に立地し、冬季は気温が氷点下になる寒冷地である。A部の変状の原因について、1つ目は塩害によるものと推定する。その理由は道路より凍結防止剤を含んだ水分が侵入し、コンクリートの変状が生じたと考えられるからである。2つ目は凍害によるものと推定する。コンクリートに内在する水分と伸縮装置部から流れ込む凍結防止剤を含んだ水分が凍結する環境下にあるためである。環境条件よりA部は南面で日当たり良好であり、夜間に凍結した状態が昼間には日差し等により融解し、凍結融解の繰り返し回数が大きくなる。その結果、長年の経過によりスケーリングや剥落が生じたと推定する。
問2
経過観察のまま5年後(2030年)、どのような状態になっているか述べる。A部は中性化深さが37.8mmとかぶりを超えており、凍結防止剤と水分が5年間侵入して塩化物イオン等が増加する可能性もあるため、鉄筋が腐食し、かぶりコンクリートの剥落やひび割れ等が増加すると推定する。B部は残存膨張量が1990年から2010年の間で減少しており、現在から5年後には膨張率はほぼゼロに近いと推定する。中性化深さも5年後は25mmでかぶりまで10mm以上残り、塩化物イオン量も腐食発生限界値には達していないため、現状と変わらない状態にあると推定する。
問3
今後20年供用するための対策方法を提案する。A部はまず塩害の要素である凍結防止剤を含んだ水分の侵入を遮断するため、伸縮装置及び排水施設の取り替えを行う。劣化箇所は鉄筋の裏側まではつり取り、防錆処理を行い、ポリマーセメントモルタルにて断面修復を行う。さらに水分等の侵入を抑制するため、表面被覆工法を行う。
B部の変状の発生原因については、使用骨材の粗骨材砕石に反応性鉱物が存在し、凍結防止剤のアルカリ成分と反応した結果、写真に見られる白色析出物がアルカリシリカゲルとなり、膨張ひび割れが発生したと推定する。その対策として、今後は水の供給を抑制するため、表面被覆工法を行う。このような対策を講じても恒久的なものではないため、定期的な点検を実施し、早期に発見して対応していくことが重要である。
25年診断士試験再現論文(2人目)
問1
A部変状の2つの原因とその理由について。
①凍結融解によるスケーリングが発生したためと推察する。理由として、表1から日最低気温(1月)が-2.4℃のため凍結し、南面のため日射により融解する。さらに上部から凍結防止剤による塩分を含んだ水が供給されるため、スケーリングが進行したと考えられる。
②中性化および塩害の複合劣化と推察する。理由は、凍結防止剤の散布により塩害が進行したこと、中性化の進行により中性化位置より内部で塩分濃縮が生じ、深さ40mmで塩化物イオン量が2.5kg/㎥以上となっている点である。その結果、鉄筋が腐食・膨張し、かぶりコンクリートの剥落が生じたと推定される。
問2
5年後のA部およびB部の状態について。
A部:スケーリングによる剥落および中性化と塩害の複合劣化がさらに進行すると推察する。 その理由は、凍害による凍結融解の繰り返しが毎年発生すると同時に、冬期には凍結防止剤が散布され、塩分を伴った水分が供給され続けるためである。
B部:大きな進展はないと推察する。その理由は、表2の残存膨張率試験により、1990年の膨張率が0.15%に対し2010年には0.05%未満となっており、アルカリシリカ反応の膨張が収束していると考えられるからである。また、全塩化物イオン量も鉄筋腐食を生じるほど高くなく、中性化残りも20mm程度確保されているため、中性化による鉄筋腐食が進展する可能性は低いと推察される。
問3
今後20年共用するための対策とその理由について。
A部:まず伸縮装置を含む上部構造物を改修し、水分の供給を絶つことが必要である。その上で変状発生部分をはつり取り、断面修復を行う。その際、全塩化物イオン濃度が腐食発生限界濃度以下となる部分まではつり取り、鉄筋の防錆処理や必要に応じた取替を実施する。
B部:変状発生部分をはつり取り、断面修復を行った上で、シラン系含浸剤による表面含浸工法を実施する。断面修復時には鉄筋の状態を確認し、必要に応じて防錆剤を塗布する。表面処理により劣化因子である水分の供給を断つことで、再劣化や新たな変状発生を予防できる。
さらに、今後20年の共用を確実にするためには点検を強化し、変状が発生し次第、速やかに対応できる体制を構築することが重要である。
どこで差がついたのか?解説します。
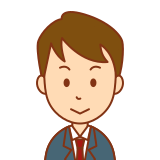
わたくしコンクリート診断士がこの2つの合格論文を徹底解説していきます。
仮名:桃田さん、40代、四択正解率27/40 67.5% の合格論文の解説です。
問題文で問われていることを繰り返し示すことで、その問いに対してしっかりと説明していることがよくわかる構成となっている。また、そのような考えに至った理由についても、「その理由は○○である」という言い回しを用いており、読み手にとって理解しやすい表現になっている。中性化深さについても、5年後には進行値がこれくらいになると示している点が良い。さらに、数値に基づいた分析が述べられているため、根拠がしっかりしていると判断できる。
劣化予測についても明確に示されており、とてもわかりやすい表現となっている。対策についてはやや物足りなさを感じるものの、的を射た具体的な施工順序が示されており、わかりやすい内容である。劣化原因から対応策まで一貫して記述されているため、読み手にすっと伝わってくる。
最後は、「この施工を行っても恒久的ではない」ことを強調し、定期的な点検を実施して再劣化を早期に発見し、適切に対応する必要があると締めくくっている点も良い。ここには維持管理の視点が感じられる。
全体的に、最初から最後までロジカルにまとめられた文書構成となっていると感じた。
仮名:空さん、50代、四択正解率27/40 67.5% の合格論文の解説です。
この文章においても、問いで問われていることを箇条書きで記載しており、正面からそれについて説明する文書構成になっている。また、A文やB部などを区別して記載しているため、何が書かれているかがとてもわかりやすい構造となっている。
次に数値化については、中性化に関する具体的な数値は示されていないものの、それに代わる腐食発生限界値や問題文の数値を用いて説明しており、1つ前の論文とは異なる数値の使い方をしている。この展開についても具体的に説明されているため、説得力がある。
さらに、5年後のA部・B部の劣化予測も明確に述べられており、メリハリのある文章となっている。対応策についても簡潔かつ的確に示されており、読み手に十分理解できる展開となっている。この文章も劣化原因から対応策まで一貫して記述されており、違和感なく読める。
また、補修後の点検の必要性や、速やかに対応できる体制の重要性についても触れており、維持管理の視点がしっかり表現されている。全体的にまとまりのある文書構成であると評価できる。
まとめ
ここまで2つの合格論文を見てきたが、いずれもロジカルな展開でとても読みやすく、わかりやすい文書構成となっていました。問いに対して的確に回答できていることからも、間違いなく合格論文であると感じられるものだったと思います。
皆さんはどのように感じ取られたでしょうか。「自分でもこれならできそうだ」と思う方もいれば、「そうは言ってもなかなか難しい」と思う方もいるでしょう。しかし、このような論文を書けるようになるには、やはり勉強時間の確保や、合格論文を知ることがもっとも大切です。ぜひ皆さんも、今回紹介した2つの合格論文を参考に学習を進めてみてください。
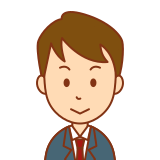
最後に今回2人の方に合格論文の提供をして頂きました。桃田さん、空さんにはお忙しいところご対応して頂き、感謝申し上げます。誠にありがとうございました。今後のご活躍を心より応援しております。
なお、当ブログではこのような👇「合格論文のテンプレート」を準備👇しており、加えて丁寧な解説も行っています。興味のある方はぜひ覗いてみてください。
では。
【2026年版】記述式が苦手でも合格できる!220人が使ったコンクリート診断士テンプレート
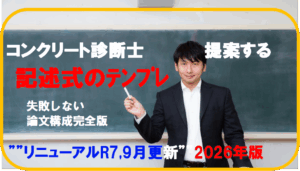
【2025年コンクリート診断士試験】一発合格者の体験記を紹介!!

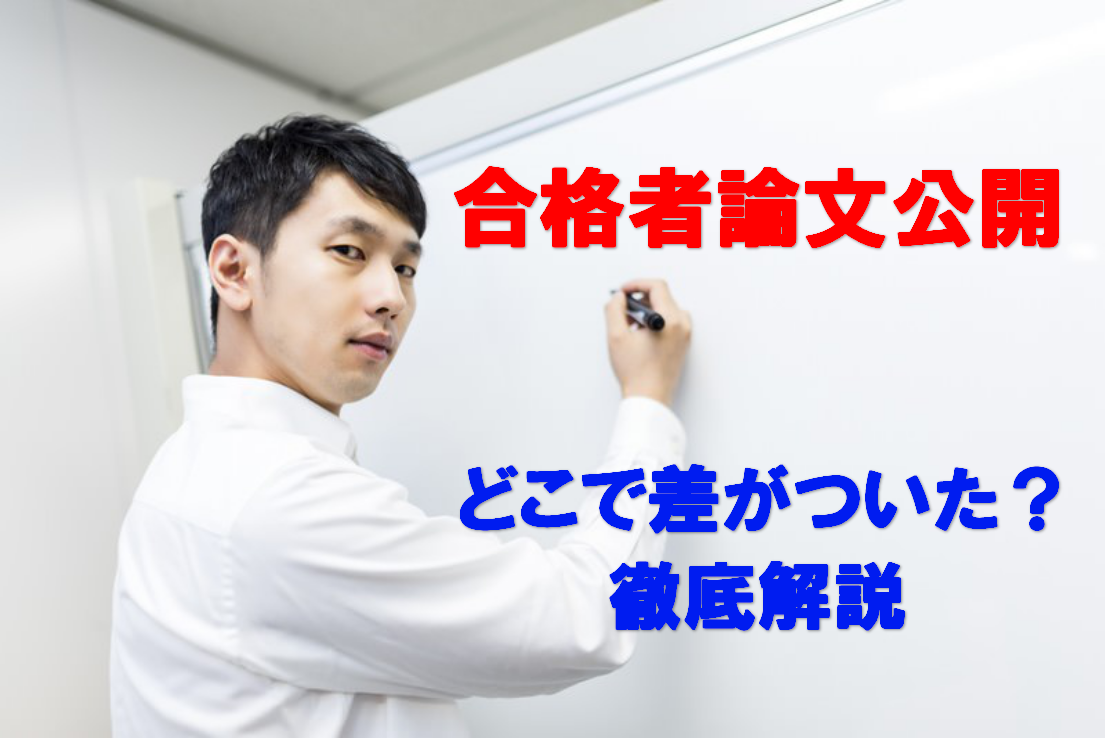

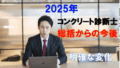
コメント