こんにちは! ポッキーでございます。
コンクリート主任技士という資格に興味を持っていただき、本当にありがとうございます!コンクリートは奥が深くて面白いですよね。
私はコンクリート診断士とコンクリート主任技士の両方を取得しています。今回は、コンクリートのプロを目指す皆さんが知りたい、主任技士の「難易度」「必要な仕事」「試験の傾向と対策」について、私の経験も踏まえて、熱く語っていきたいと思いますので、最後までご覧ください。
1. コンクリート主任技士とは? その価値と求められる役割
コンクリート主任技士は、**公益社団法人日本コンクリート工学会(JCI)**が実施する民間の上位資格です。単なる現場作業員ではなく、高度な技術を持った専門技術者として認められます。
資格の持つ高い価値と社会的役割
この資格の大きな価値は、その公的な位置づけにあります。 国土交通省の「土木工事共通仕様書」や土木学会の「コンクリート標準示方書」、日本建築学会の「JASS 5 鉄筋コンクリート工事」といった公的文書にも明記されています。
さらに、公共工事の品質確保促進法(品確法)に基づき、一定規模以上のコンクリート工事現場への配置が法的に義務付けられています。具体的には、工事費が3,500万円以上の鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、プレストレストコンクリート造の工事において、監理技術者補佐または主任技術者としての配置が求められる、非常に重要な資格なんです。
技士との決定的な違い
主任技士は、コンクリート技士の上位資格として位置づけられています。 技士が主に現場レベルでの品質管理を担当するのに対し、主任技士は以下のようなより高次元の責任を負います。
1. プロジェクト全体の統括管理
2. 複数現場の技術指導
3. 品質管理計画の策定・実行
4. コンクリートの製造、工事および研究における計画、管理、指導等
知識レベルでも、技士の能力に加え、JISに規定されている試験方法以外の応用試験の計画・実施能力、特殊なコンクリートの配合決定能力、そして品質変動要因を総合的に捉えた製造方法・品質管理基準の立案能力が求められます。
キャリアと年収の展望
主任技士の資格取得は、建設業界でのキャリアアップと年収向上を実現する最も確実な方法の一つです。 資格手当は、技士の1.5〜2倍程度に設定している企業が多いんですよ。
• 大手ゼネコン:主任技士取得時で年収600〜750万円、所長クラスで年収1,000〜1,300万円が目指せます。少し聞いた限りでは、スーパーゼネコンの〇〇は、中途採用でも1000万~1500万ほどあるらしいですよ。夢がありますね。
• 資格手当:月額3〜5万円(年間36〜60万円)が相場です。
特に2025年以降、大型インフラ整備が本格化しており、有資格者の市場価値は過去最高水準に達しています。転職市場では、コンクリート主任技士の求人倍率は約3.2倍と、完全に売り手市場が続いています。ちなみに私は取得していますが、手当が付くなら1万円程度です。ただ、それよりも上位の資格があれば、そちらが優先される仕組みです。
2. 難関資格の扉を開く!難易度と受験資格
コンクリート主任技士は、決して簡単な試験ではありません。しかし、適切な対策をすれば必ず合格できる資格です。
合格率の難しさ
コンクリート主任技士試験の合格率は、過去5年間の平均で約13%程度の難関試験として認識されています。合格基準点は公表されていませんが、択一問題で70点以上、可能であれば8割以上取れていれば合格の可能性が非常に高まります。
合格者の平均学習時間は約300時間と言われていますが、効率的な勉強法で200時間程度での合格も可能です。
受験資格の壁
主任技士の資格は、高度な実務能力を問うため、受験するには実務経験が必須となります。
|
学歴・資格
|
必要実務経験年数(コンクリート関連業務)
|
補足
|
|
大学卒(建設系学科)
|
2年以上
|
–
|
|
高校卒
|
7年以上
|
–
|
|
コンクリート技士保有者
|
技士資格取得後2年以上
|
–
|
|
A1~A8の資格登録者
|
実務経歴書の記入・証明は不要
|
例:技術士(建設部門)、1級土木・建築施工管理技士(監理技術者資格者証保有者)
|
【ポッキーからのアドバイス】 受験資格の証明となる「実務経験証明書」の書き方は非常に重要です。単なる「現場監督」という記載ではなく、「RC造集合住宅建設工事において、コンクリート品質管理計画の策定から打設管理、養生管理、品質試験の実施・評価まで一貫して担当した」といった具体的な記述が求められます。数値データ(構造物規模、コンクリート使用量など)を盛り込むと、審査担当者に強い印象を与えられますよ。
3. 試験内容の傾向と対策:四肢択一と記述式を徹底分析
主任技士試験は、四肢択一問題と記述式(小論文)で構成されています。試験時間は3時間と短縮されており(令和2年から)、簡潔にまとめる能力が以前よりも重要になっています。
四肢択一問題の攻略法
択一問題で8割以上を確保することが、合格への近道です。試験科目は、大きく分けて以下の4分野です。
|
科目
|
重点ポイント
|
対策のコツ
|
|
材料
|
セメント(組成、水和熱、種類)、骨材(品質要件、JIS規格、粒度)、混和材(フライアッシュ、高炉スラグ)、高性能AE減水剤
|
JIS規格の数値データ(低アルカリ形セメントの全アルカリ量など)はフラッシュカード等で完全暗記しましょう。
|
|
配合・試験
|
単位水量、水セメント比、空気量などの計算問題。JIS A 1101〜1155の主要な試験手順と判定基準。スランプ試験の許容範囲や手順(3分以内、3層25回突き固め)。
|
公式の導出過程を理解し、様々なパターンの計算問題に慣れることが必須です。
|
|
施工
|
標準的な施工方法、特殊コンクリート(高強度、高流動など)の施工上の留意点。打込み(材料分離防止、打重ね時間)、締固め(振動時間5~15秒、挿入間隔50cm以下)。
|
実務経験が有利ですが、理論的な裏付け(示方書の内容)を付けて回答できるように準備しましょう。
|
|
設計・維持管理
|
コンクリート標準示方書(施工編、検査標準)の理解。老朽化対策としての点検・診断技術、補修・補強工法。劣化現象(中性化、塩害、ASR、凍害)と対策。
|
維持管理分野は出題が増加傾向にあります。点検手順(初期点検→日常点検→定期点検→劣化予測→詳細調査→補修計画)を整理しておきましょう。
|
【知識のアップデートに注意!】 2025年度の試験では、レディーミクストコンクリートのJIS A 5308が2024年3月に改正された内容が反映される可能性があります。過去問の答えが、最新の規格では誤答になっている場合があるので、常に最新の情報(特に規格や基準の変更点)を反映させながら学習を進めることが不可欠です。
記述式(小論文)の出題傾向とポッキー流テンプレート攻略法
記述式は、コンクリート主任技士としての資質と、社会的な背景を踏まえた技術的課題への取り組みが問われる問題が1題に統合されています。
選考基準は「与えられた課題について、実務経験を踏まえた内容の小論文を記述する能力」です。
記述式で最も重要な3つのテーマ
私が過去問を分析し、最も出題傾向が高いと考えているのは、コンクリート主任技士の倫理規程にもある「持続可能な社会の貢献」に付随する以下の3項目です。
1. コンクリート分野における環境負荷低減
2. コンクリート構造物の耐久性向上
3. コンクリート構造物の現場施工における生産性向上
これらのテーマについて、メリットやデメリットを踏まえた解決策を提案する練習をすることが、具体的な勉強方法になります。
ポッキー流!論文作成テンプレート(基本の流れ)
記述式が苦手な方でも合格レベルに到達できるように、論理的な構成を確立することが重要です。試験時間が短いため、事前にテンプレートを準備し、必要なキーワードを当てはめる練習をしましょう。
論文の基本の展開は、この3つの流れで書き進めれば問題ありません。
|
展開
|
内容の核
|
ポイント
|
|
① 序論(背景と技術的知見)
|
テーマに対する我が国の一般的な現状と課題。具体的な数字を交える。
|
例:セメント製造による排出量(国全体の約5%)や、建設廃棄物のリサイクル率など。
|
|
② 本文(業務の現状と課題)
|
あなたの業務(生コンプラント、現場監督など)の立場を明確にし、テーマに関連する現状と、そこから生じる具体的な課題。
|
経験談を交えることで説得力が向上します。
|
|
③ 結論(取り組みと展望)
|
課題に対する具体的な取り組み(解決策)を2つ程度提案し、その効果(成果)や今後の展望を述べる。
|
提案→実行→効果の順に書くと採点されやすいです。
|
【記述の具体的なテクニック】
• 時間配分:択一問題に75分、**小論文に1時間45分(105分)**を確保しましょう。
• 短文主義:1文は長くても70字までにおさめ、理想は60字程度です。1文には言いたいことを1つだけ入れましょう。
• 論理的な文章:曖昧な表現を避け、「~である」と簡潔で明確に記述します。接続助詞(から、が、ためなど)の繰り返しを避けることも大切です。
• 具体性:抽象的な表現ではなく、数値データや規格番号を記述することで、専門性が高まり良い印象を与えられます。
テーマ別キーワードの活用例
1. 環境負荷低減 最重要テーマは「カーボンニュートラル」と「資源循環」です。
• 課題: セメント製造過程での排出。コンクリート塊のほとんどが路盤材への利用に留まり、コンクリート用再生骨材としての活用が不十分であること。
• 対策: フライアッシュや高炉スラグなどの混和材を大容量で積極的に使用し、セメント量を削減する。リサイクルに向けた基準の整備や、技術革新による低コストのリサイクル設備の開発も課題です。再生骨材の利用は、廃棄物削減だけでなく、採掘・輸送に伴う温室効果ガスの削減にも繋がります。
2. 耐久性の向上 老朽化対策、少子高齢化による維持管理費増加、激甚化する自然災害対策の観点から重要です。
• 劣化対策の例:
◦ 塩害対策:水セメント比を小さくしてコンクリート組織を緻密化する。かぶりを大きくする。エポキシ樹脂で加工された鉄筋を用いる。高炉セメントを使用する(塩化物イオン固定化効果)。
◦ ひび割れ対策:単位水量を低減する。混和材(低熱セメント、膨張材)を活用し水和熱を抑制する。再振動を実施し、鉄筋や粗骨材の下に溜まった水や空気を除去して密実化を図る。
3. 生産性の向上 労働力不足の深刻化(ピーク時から約32%減少)への対応策として重要です。
• 解決策: プレキャスト化の活用。現場施工期間の短縮や工場生産による品質向上(天候の影響を受けない)が期待できます。ただし、接合部耐力の実証や型枠コストが課題です。
• 新技術: 締固め不要の高流動コンクリートの利用。複雑な形状や過密配筋部にも密実に充填できるため、締固め作業の省力化・効率化に大きく貢献します。また、新型バケットとOKホースを組み合わせたシステムのように、硬練りコンクリートでも材料分離なくスムーズに運搬・打設する技術も開発されています。これは空気量の減少も抑制でき、凍害防止にも優位性があります。
4. 合格を勝ち取るための具体的な学習計画
私ポッキーが合格を勝ち取ったときも、戦略的な学習計画が不可欠でした。
① 真のバイブルの活用
コンクリート主任技士の試験対策において、私が先輩から教えてもらった**「真のバイブル」があります。それは、コンクリート工学会が毎年内容を更新して出版している「コンクリート技術の要点」**です。
ほぼ全ての過去問の答えは、このテキストのどこかに書いてあります。通読は必須ではありませんが、問題集の解説を読んで分からない部分があれば、辞書代わりにこの本で調べることが劇的に効率的です。私は、通読したことで仕事の幅が相当に広がったと感じていますよ。
② 過去問演習の徹底
資格勉強の王道は、過去問演習です。私は2回目の受験時に問題集3冊を5周しました。
過去問を解く際は、単に答えを覚えるのではなく、「なぜその答えが正しいのか、理論的背景を理解すること」応用力が身につきます。
③ 体系的な学習スケジュールの確立
合格者の平均学習時間(約300時間)を確保するために、計画的な学習が必要です。
|
期間
|
内容
|
目的
|
|
第1〜2ヶ月
|
基礎知識の習得(要点通読、基本用語の理解)
|
知識の土台作り
|
|
第3〜4ヶ月
|
過去問演習と弱点分析(過去5年分を最低3回実施)
|
出題傾向の把握、知識の定着
|
|
第5ヶ月
|
応用問題演習と記述対策(予想問題集、論文作成練習)
|
応用力強化、論文のテンプレート習熟
|
|
第6ヶ月
|
総復習と実戦演習(模擬試験、最終チェック)
|
本番への慣れ、最新情報の確認
|
④ 記述式の事前準備(デメリットからの解決策)
記述式は、準備さえしておけば十分合格点が取れる問題です。
テーマに対して、現状のデメリット(課題)解決策を提案する練習をしてください。
• 例:耐久性向上の課題は、劣化機構(中性化、塩害など)が挙げられます。これに対して、水セメント比の低減、適切な養生、密実な締固め、または高性能AE減水剤やフライアッシュ等の混和材を活用するなどの解決策を整理しておきます。
5. コンクリート主任技士としての未来
コンクリート主任技士の資格は、取得がゴールではありません。資格を活用して、どのようなキャリアを築きたいかを明確にすることが重要です。
建設業界は今、老朽化対策、カーボンニュートラル、DX化など、大きな変革期を迎えています。設計、材料、施工、維持管理(巡回・巡視)を含めたライフサイクル全体を考慮することが、合理性、経済性の観点からも必要不可欠です。
主任技士は、まさにそのライフサイクル全体をマネジメントし、品質を保証する役割を担うことになるのです。
不適切な構造物が社会にもたらす影響は甚大です。だからこそ、主任技士として、不良な構造物を生み出さない仕組みを構築し、安全で安心、そして持続可能な社会の構築のために貢献することが求められます。
さあ、あなたもコンクリート主任技士として、建設業界の未来を切り開く一員となりませんか!
おすすめ記事はこちらから👇
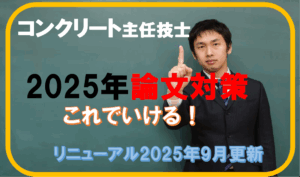

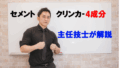
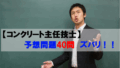
コメント