皆さん、こんにちは!ポッキーです。
この記事は、コンクリートをあまり知らない方に向けて発信する内容です。当ブログからのご意見で「コンクリート技士などに関する記事が少ない」という声がありました。今回はそれに答えた記事を作成しました。これから、コンクリート技士を目指してみようとか、もしくは、興味本位でコンクリートの事を知りたいと思った方にはささる記事のなっています。ぜひ最後までご覧ください。
私たちの生活を支える建物や橋、道路など、どこを見ても存在しているのが
コンクリートです。
あまりにも身近すぎて、その性質について深く考える機会は少ないかもしれません。しかし、この灰色の素材には、私たちが安全・安心に暮らすための驚くべき秘密と、長く使うために注意すべき大切なポイントが隠されています。
これから、「コンクリートってセメントと砂利を混ぜたものでしょ?」という初心者の方に向けて、その基本的な特徴、硬化前後の性質、そして構造物を長持ちさせるために必要な知識を、わかりやすく解説していきます。
1. コンクリートの基本:何からできているの?
コンクリートは、主に4つの材料を混ぜ合わせて作られる複合材料です。
|
材料名
|
役 割
|
|
セメント
|
**接着剤(結合材)**の役割を果たし、水と反応して固まることで強度を生む。
|
|
水
|
セメントと化学反応(水和反応)を起こさせ、コンクリートを硬化させる。
|
|
骨材
|
コンクリートの骨格を形成する材料。砂、砂利、砕石などが使われる。
|
|
混和材料
|
必要に応じて特定の性能(例:流動性向上、耐久性向上)を付与するために添加される。
|
セメントは、主に石灰石、粘土、けい石などを高温で焼成して作られる「水硬性セメント」の一種であるポルトランドセメントが一般的です。
環境面では、脱炭素が謳われています。セメントを高温で燃焼させる際に、多くの二酸化炭素が発生します。この発生を抑制するために低炭素型コンクリートがあります。これは、主にセメントの一部を高炉スラグ微粉末に替え使用することで、CO₂排出量を削減するものです。
国土交通省の定義では、ポルトランドセメントの55%以上を置換したもの、またはそれと同等のCO₂削減効果があるものを「低炭素型コンクリート」と呼びます。
骨材は、粒の大きさによって、10mmふるいを全て通過する「細骨材」(砂)と、5mmふるいに85%以上とどまる「粗骨材」(砂利や砕石)に分類されます。骨材は清浄で堅硬であり、化学的・物理的に安定していることが求められます。
2. 生コンクリート(フレッシュコンクリート)の性質と施工上の注意点
まだ固まっていない、工場から現場に運ばれてきたばかりのコンクリートをフレッシュコンクリート、または生コンクリートと呼びます。この段階での取り扱いが、最終的な構造物の品質を大きく左右します。
(1) 作業性(ワーカビリティー)を確保する
フレッシュコンクリートの重要な性質の一つが「ワーカビリティー」(作業性)です。これは、練混ぜから型枠への打込み、締固め、仕上げまでの作業のしやすさを示す指標です。
ワーカビリティーは、主にコンシステンシー(変形・流動に対する抵抗性)と材料分離抵抗性(分離しにくさ)で評価されます。
一般的に、水の量(単位水量)が多いほどコンシステンシー(流動性)は増しますが、水の量を増やしすぎると、分離しやすくなったり、強度や耐久性が低下したりするため注意が必要です。
(2) 品質を左右する材料分離とブリーディング
コンクリートを打ち込む際に、材料が均一でなくなる現象を材料分離といいます。特に、粒径の大きな粗骨材が分離しやすい性質があります。
また、セメントや骨材が沈降し、水が上部に浮き上がってくる現象をブリーディング(水の分離)と呼びます。ブリーディング量が多いと、鉄筋の上部にひび割れ(沈下ひび割れ)が発生しやすくなったり、打ち継ぎ部分の接着力が低下したりする懸念があります。
(3) 施工中の不具合を防ぐための重要ポイント
打込みと締固めの工程で不具合が発生すると、構造物の耐久性は施工直後から大きく影響を受けてしまいます。
1. ジャンカ(あばた、豆板)を防ぐ
◦ 原因: 鉄筋などが障害となり、コンクリートが型枠の隅々まで行き渡らず、締固めが不十分なときに発生します。
◦ 対策: バイブレータで十分に締固めることが必須です。所定のワーカビリティー(作業性)を持つコンクリートを使用し、鉄筋のかぶりやあきを十分にとることも大切です。
2. コールドジョイントを防ぐ
◦ 原因: すでに打ち込まれた下層のコンクリートが凝結し始めている上に、新しいコンクリートを打ち重ねた際、両者が一体とならない継ぎ目ができてしまう現象です。これがトンネルなどで発生すると、剥離による第三者障害の危険性があり、鉄筋コンクリートでは鋼材の腐食を増進させます。
◦ 対策: 上層を打設する際に、下層とともに十分に締固めること。また、適切な打ち重ね間隔を確保し、特に暑い時期(暑中時)には、生コン車の配車に余裕を持った計画が必要です。凝結遅延剤を適切に使用することも有効です。
3. 温度ひび割れを防ぐ
◦ 原因: セメントが水と反応する際に発生する水和熱に起因します。コンクリートの内部と外部で温度差が生じたり、岩盤などに拘束されたりすることで、ひび割れが発生します。
◦ 対策: 発熱量の少ないセメント(低熱、中庸熱など)を用いる。高性能な混和材料(高性能AE減水剤、フライアッシュなど)を活用する。打ち込み温度を低く抑えることで、水和熱の発生を抑制します。
3. 硬化したコンクリートの驚くべき性質
コンクリートが硬化すると、その構造物としての性能は計り知れないものになります。
(1) 強度が強い:圧縮力に優れる
硬化したコンクリートの最も重要な性質は圧縮強度です。コンクリートは、上から押しつぶす力(圧縮力)に対して非常に強く、設計においてもこの圧縮強度が代表的な指標とされます。他の強度(引張強度など)も、圧縮強度から推定することが可能です。
• 引張強度との違い:
◦ コンクリートは、引っ張る力(引張強度)に対しては、圧縮強度のわずか1/10~1/13程度しか持ちません。これが、コンクリートを鉄筋(引っ張りに強い)で補強する鉄筋コンクリート構造が主流である理由の一つです。
また、練混ぜ時間が長いほどセメントと水がよく接触して強度が大きくなりますが、空気量が増加すると、水セメント比(W/C)が一定の場合でも強度は低下する傾向があります(空気量1%増加で4~6%の強度低下)。
(2) 構造物を長寿命化する水密性と体積変化
水密性とは、コンクリート内部への水の浸入を防ぐ能力です。水密性を悪くする最大の要因は、ジャンカやひび割れなどの施工欠陥です。
施工欠陥がない場合、水密性を確保するには、セメントに対して水の割合を示す水セメント比(W/C)を小さくすることが非常に重要です。W/Cが55%以上になると、セメントペーストの水密性は著しく低下するとされており、水密性を確保する調合ではW/Cが50%以下と規定されています。
体積変化にも注意が必要です。
1. 乾燥収縮:
◦ 硬化したコンクリートは、乾燥によって体積が収縮します。これが周囲に拘束されるとひび割れが発生します。
◦ 単位水量の多さが収縮に最も大きく影響します。単位セメント量が多い高流動コンクリートや高強度コンクリートでは、セメントの水和による自己収縮も考慮が必要です。
2. 熱膨張:
◦ コンクリートの熱膨張係数(温度上昇による体積膨張の割合)は、埋め込まれている鉄筋とほとんど同じです。この性質があるため、鉄筋とコンクリートが一体となって温度変化に対応でき、鉄筋コンクリート構造が成り立つ重要な前提となっています。
4. コンクリートの寿命を縮める「劣化の要因」と予防策
コンクリート構造物の耐久性を阻害する要因は、「施工中の不具合」(前述)と、供用期間中に発生する「経年劣化」に分けられます。ここでは、特に鉄筋コンクリートの寿命を脅かす主要な劣化現象を見ていきましょう。
(1) 中性化(ちゅうせいか)
中性化は、空気中の炭酸ガスがコンクリートのアルカリ性(pH12~13)を中和し、pHを低下させる現象です。
• 劣化要因: 鉄筋コンクリートでは、コンクリートの強アルカリ性によって鉄筋の表面に保護膜ができ、錆びるのを防いでいます。中性化が進んでpHが低下すると、この防錆効果が失われ、鉄筋が腐食する可能性が高まります。
• 対策:
◦ かぶりを十分にとる(鉄筋を覆うコンクリートの厚さ)。
◦ 水セメント比(W/C)の小さい、密実なコンクリートとすること。
(2) 塩害(えんがい)
塩害は、コンクリート中の塩化物イオンが鋼材の腐食を促進させ、腐食生成物が体積膨張を起こすことで、ひび割れや剥離を引き起こす現象です。
• 侵入経路:
◦ コンクリートの製造時(海砂の除塩不足や塩化物を含む混和剤の使用など)。
◦ 外部からの浸透(海からの飛来塩分や凍結防止剤など)。
• 対策:
◦ かぶりを十分にとること。
◦ 水セメント比(W/C)の小さい、密実なコンクリートとすること。
◦ コンクリートを練り混ぜる際の塩化物の総量を規制すること。
◦ エポキシ樹脂塗装鉄筋などの使用も検討される。
(3) アルカリ骨材反応(ASR)
アルカリ骨材反応は、骨材(砂利や砕石)に含まれる反応性の鉱物が、セメントから生じる水酸化アルカリと反応し、その生成物が吸水・膨張することでコンクリートに大きなひび割れを生じさせる現象です。
• 対策:
◦ 反応性の疑いのある骨材を使用しない。
◦ コンクリート中のアルカリ総量を規制する。
◦ 反応抑制効果が明らかなセメント(高炉セメントなど)を使用する。
5. 長持ちさせるための「維持管理」と未来の技術
コンクリート構造物を長く、安全に使い続けるためには、設計・施工だけでなく、完成後の維持管理が不可欠です。
(1) ライフサイクル全体を考える
かつてコンクリートは「メンテナンスフリー」と考えられていた時代もありましたが、塩害やアルカリ骨材反応による早期劣化が社会問題となり、維持管理の重要性が再認識されています。
維持管理の目的は、構造物が所要の耐用期間中にその性能を十分に発揮させることにあります。そのために、竣工後の初期点検から始まり、日常点検、定期点検を通じて、劣化を予測し、詳細調査を経て補修・補強計画を立てるという手順が重要となります。
今後は、劣化が表面化した箇所だけでなく、化学的・物理的な経年劣化が生じていることを認識し、構造物全体を対象とした維持管理へと移行すると考えられています。
(2) 構造物の健康診断:非破壊試験
構造物全体を対象とし、劣化を早期に検出するためには、構造物を壊さずに内部を調べる非破壊検査(モニタリング)が重要になります。
• 強度推定: 反発度法(シュミットハンマー)は、コンクリート表面を打撃した反発の程度から強度を推定する簡便な方法です。
• ひび割れ・空洞検出: 弾性波法(超音波法など)は、反射波を分析してひび割れや空洞を検知します。また、AE法(アコースティック・エミッション)は、ひび割れ発生時に伝播する弾性波を検出し、リアルタイムでの連続監視への適用が期待されています。
• 鉄筋位置・かぶり厚さ: 電磁誘導法や電磁波レーダ法を用いて、鉄筋の位置や、コンクリートが鉄筋を覆っている厚さ(かぶり厚さ)を推定します。
(3) 環境への配慮:再生と高性能化
持続可能な社会の構築に向けて、コンクリート分野ではゼロエミッション(廃棄物ゼロ)を目指す取り組みが不可欠です。
1. 資源のリサイクル:
◦ 火力発電所の副産物であるフライアッシュや、製鉄所の高炉スラグ微粉末は、コンクリートの品質向上や環境負荷低減に貢献する混和材として広く利用されています。
◦ 解体で生じるコンクリート塊(コンクリートガラ)のほとんどは路盤材などに再利用されていますが、再生骨材としてコンクリートに再利用する取り組みも進められています。高品質な再生骨材(骨材H)を製造すれば天然骨材と同等品質のコンクリートが製造可能ですが、製造コストや品質のばらつきが課題となっています。
2. 高性能コンクリートの活用:
◦ 高流動コンクリート(HFC)は、高い流動性と分離抵抗性を兼ね備え、締固めが不要な自己充填性を有しています。これは、鉄筋が密集した複雑な構造物にも密実にコンクリートを充填できるため、施工の省力化・合理化に大きく貢献します。ただし、局所的な充填不良が発生した場合に振動締固めで対応できないため、受け入れ時の検査は全数検査が原則となります。
まとめ
コンクリートは、私たちが当たり前に享受しているインフラの安全と耐久性を支える「縁の下の力持ち」です。その強さと、時間とともに進行する劣化の特性を理解し、設計、施工、そして維持管理のライフサイクル全体を通じて適切に関わっていくことが、未来にわたってこの豊かな社会基盤を維持していく鍵となります。
コンクリートの性質を理解することは、単なる知識ではなく「劣化診断や補修設計」の根本を理解することにつながります。
たとえば中性化や塩害の進行は、セメントの種類・水セメント比・施工管理など、すべて「材料段階の選定」に起因します。
主任技士や診断士の試験では、こうした材料特性と構造物の寿命をどう結びつけるかが記述式で問われる傾向があります。
つまり、「なぜ強いか」を学ぶことは、「なぜ劣化するか」「どう防ぐか」を理解する第一歩なのです。
この考え方がわかると、設計・施工・維持管理を一貫して論理的に説明できるようになり、試験だけでなく実務にも大きく役立ちます。
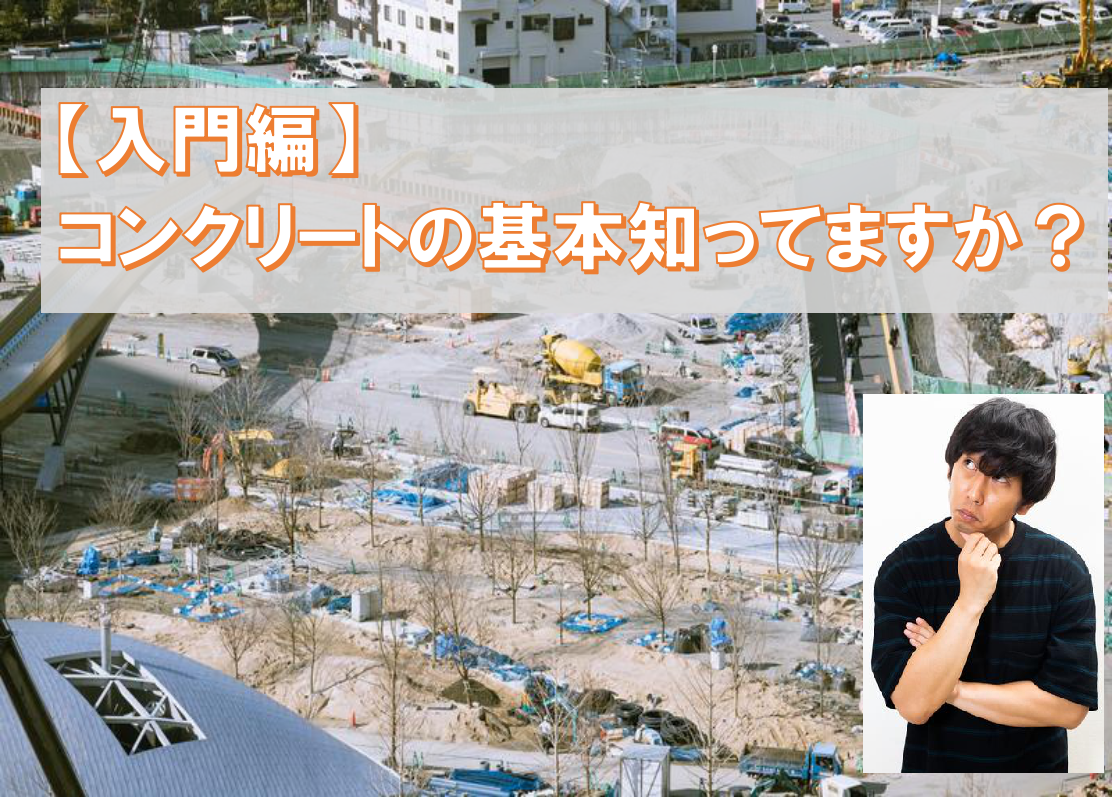
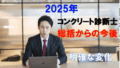
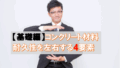
コメント