今回は補修補強方法について説明したいと思います。

四択問題でも2割前後の出題率なので、重要項目になります。
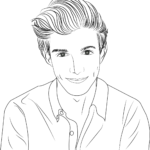 私は、コンクリート診断士、コンクリート主任技士を取得しています。
私は、コンクリート診断士、コンクリート主任技士を取得しています。
特に、コンクリート診断士の取得を目指している方に有益な情報を発信すること目指しています。
補修・補強方法はいろいろ種類がありますが、まずは、劣化現象毎に整理をしていきましょう。
そうすると、自ずと頭に入ってくると思います。
補修・補強方法とは
これまで劣化現象についてのメカニズム、その調査方法などをみてきました。
劣化現象や調査方法の大きなイメージが付けば、わからない問題が出題されても何となく答えを出せるのではないかと思います。
過去問は大事ですが、一番は自分で各現象の大枠を理解しておけば自分なりの考えで答えを出せるはずです。
だだし、塩害や中性化、火害が特有の補修方法があります。
では、まずは、塩害と中性化、火害の補修方法をみていきます。
1.塩害の補修方法
脱塩工法(電気化学的補修工法)
脱塩工法は、文字通り塩分を排除する工法です。金額的には高価なので、論文では、最悪は脱塩工法の検討をする。というような書きっぷりとなります。
〇原理
1~2A/m2 の直流電流を8 週間(2 か月)流します。電解質溶液として水酸化カルシウムまたは、ホウ酸リチウムをコンクリート面に設置します。すると塩分であるCl-が電気泳動して溶液側に集まります。これで塩分が排除できます。
※これは丸暗記です。
2.中性化(火害)の補修方法
再アルカリ化工法
この工法は、中性化と火害を受けた場合、コンクリート内にアルカリ分を浸透させるものです。(火害は500~580℃で中性化するため)
〇原理
これも脱塩工法と同様に1~2A/m2 の直流電流を1~2 週間流します。コンクリート面に、陽極材として炭酸カリウムのアルカリ溶液をセットします。そうするとアルカリ分がコンクリート内に浸透する原理です。注意が少しあります。
再アルカリ化工法終了後は、速やかに表面被覆工法をする必要があります。
理由は、雨水などがかかるとせっかくのアルカリ性溶液が外に流出するからです。また、PC 鋼材の水素脆弱が懸念されるため、事前の検討が必要になります。
加えて、アルカリ分を浸透させるため、ASR を引き起こす可能があるので注意が必要です。
先ほども言いましたが、この2 つは限定される劣化に対向した工法になります。
ここからは、劣化過程での状況で決定されるものなので劣化状況別に解説します。
3.劣化過程による補修方法
4.まとめ
補修補強方法は、劣化状況で判断し決定します
劣化現象の劣化過程ごとの補修方法を理解していきましょう。すると、異なる劣化現象でも同じ補修工法を使用していることが分かります。つまり、補修方法はどれも同じような方法なのです。それは、なぜかというと、鉄筋が錆びていれば防錆をします。鉄筋が錆びる現象は、中性化、塩害、ASR、凍害、疲労、火害、化学的侵食になります。そうです。全ての劣化現象に当てはまることが分かります。加えて、断面修復が必要なのも鉄筋が錆びて剥離剥落するから必要な工法です。なのでこれも劣化現象全てに当てはまります。
ただしこれにアクセントを付け加えるとしたら、ASRには亜硝酸リチウムを混入した断面修復材を使用するなど劣化現象の特徴を抑制するような材料名を具体的に書くことで、添削者からの印象をアップされることができるはずです。
補修後は、劣化因子の侵入を抑制するための表面を保護する補修工法を考えます。中性化なら、CO2を遮断するため、表面被覆工法を施すや、塩害も同様です。
補強方法の選択は、構造物の特徴を理解する必要があります
補強方法は、劣化状況を診断したとき、ASRにより鉄筋が切断されている場合や、腐食状況が大きい場合、また、火害でコンクリート強度およびコンクリートの弾性係数が低くなっている場合、PC鋼線が切断している場合などに必要になってきます。この状態は、感覚的に構造物の耐荷性能が低下していることがわかると思います。
そして、補強工法を提案します。鉄筋の切断や腐食が大きい場合には、鉄筋を追加し増し厚することが必要となります。また、コンクリートの強度や弾性係数が低下している場合は、鋼板接着工法やRC巻き立て工法になります。PC鋼線が切断している場合は、外ケーブル工法になります。
論文では
論文では、供用年数30 年などの条件が与えらるので、基本的には現状を回復させ、プラス補修後を維持させる提案が必要になります
具体的には、塩害の場合は断面修復をします。これで現状回復できていますが、現場環境を変えることができないので10 年後には再劣化する可能性があります。そのため定期点検することにより劣化状況を把握し、必要ならば、脱塩工法が電気化学防食工法も検討しておく。と記載する。など、定期点検を行うことで早期発見し早期対応する。というシナリオがベストではないかと思っています。
補足
これまで、中性化から補修・補強方法の大まかな項目を説明してきましたが、今回が最後になります。今までの記事で大枠な事項は全て記載しましたので、皆さんの参考になればと思います。
四択問題の対応は、過去問を解きながら理解していってください。問題の傾向がわかってくると思います。
論文について、私なりの展開を述べてきましたが、皆さんの思うわかりやすい展開にしてオリジナルを出しても大丈夫です。
一番はわかりやすい文章を心掛け、複数の劣化現象を回答をする場合は、一つずつ同じような流れで説明することが大切です。
分かりやすい言い回しを意識すれば合格できると思います。
論文のテンプレートを考えました。ぜひご覧ください。



コメント