こんにちは、ポッキーでございます
コンクリート技術者の皆さん、そしてコンクリート主任技士を目指している皆さん、今回のテーマは、まさに「持続可能な社会の構築」という最重要テーマに直結する**「再生骨材」**について深く掘り下げていきたいと思います。
最近、SNSなどで皆さんとお話ししていても、環境負荷低減や資源循環に関する意識が本当に高まっているのを感じます。コンクリート主任技士の試験対策としても、「コンクリート分野における環境負荷低減」は、最重要項目の一つとして備えておくべきテーマだと私は考えているんです。

今回は、私が皆さんに語りかけるような形で、再生骨材の現状、品質、そしてこれからの展望について、たっぷりと3000文字程度で熱く語らせてください!
【再生骨材の現状】知っておくべきコンクリート廃棄物の現実
まず、なぜ私たちがこれほどまでに再生骨材に注目しなければならないのか、その背景から見ていきましょう。
私たちの社会を支えるコンクリート構造物は、いつかその役目を終えます。構造物の解体に伴って排出されるコンクリート塊の量は、とてつもなく膨大なんです。
国土交通省が2002年に調査した結果によれば、その排出量は約3500万トンに上ります。そして、この量は今後さらに増えると予測されており、なんと2050年には2億トンに達すると見られているんですよ。
もちろん、私たちコンクリート分野は古くからリサイクルに取り組んでおり、この大量のコンクリート塊のうち、約98%が再利用されているという高水準なデータがあります。
「なんだ、ちゃんとリサイクルできているじゃないか」
そう思われるかもしれません。
しかし、ここに大きな課題が潜んでいるんです。
現状、再利用されているコンクリート塊の大部分は路盤材への使用が中心なんです。つまり、コンクリートとして再び利用する、という本来の「コンクリート用再生骨材」としての活用は、いまだ十分とはいえない状況にあるわけです。
将来的に、新規の道路事業や建設工事が減少していくことが予想される中で、私たちはこうした低次な使い方から、より高品質な再生骨材(JISのHやM等級)への利用にシフト転換していくことが、喫緊の課題だと私は考えています。
【品質が命】再生骨材の製造と等級について
再生骨材を製造するプロセスは、天然の骨材とは大きく異なります。解体されたコンクリート塊を破砕し、ふるい分けをすることで得られますが、品質を向上させるためにはさらなる工夫が必要です。
製造方法としては、一次破砕材を再び破砕して粒度調整や粒形改善を行う方法、さらには機械的にすりもみして、原骨材に付着したモルタル分を除去する方法などがあります。
ここで重要なポイントは、**「付着モルタル分」**です。
高品質な再生骨材を目指せば、理論上は天然骨材と同等な、モルタル分の付着が全くない再生粗骨材や再生細骨材の製造も可能ではあります。しかし、一般的にはモルタル分が付着した状態の骨材として取り出されることが多いのが実情です。
この付着モルタル分が、再生骨材の品質のバラツキを生む最大の原因となります。原料となる解体コンクリートの品質が一定していなければ、このバラツキはさらに大きくなります。
そこで、品質を客観的に評価し、構造物への利用を適切に行うために、再生骨材はJISによって規格化されています。このJISでは、密度や吸水率などから品質の良い順にH、M、Lの3つに区分されています。
高品質なH骨材を使用すれば、天然骨材と同等な品質のコンクリートを製造することも可能ですよ。
しかし、低品質な再生骨材には問題があります。骨材の周りにモルタル分が付着しているため、吸水率が高くなり、結果としてコンクリートの単位水量が増加する傾向があるのです。
また、付着モルタルが多いほど、そして再生細骨材の割合を多くするほど、コンクリートの強度や耐凍害性が低くなる傾向があるため、コンクリートに求められる品質が得られるよう、普通骨材との組み合わせを慎重に検討する必要があるのです。
【コストの壁】普及に向けた二大課題
再生骨材の利用拡大は、環境負荷低減、すなわちゼロエミッションの考えに基づく資源の有効利用という大きな目標のために不可欠です。しかし、その普及には「品質」と「コスト」という大きな壁が立ちはだかっています。
1. 品質面の課題
先ほども述べましたが、製造後の再生骨材の表面にはモルタル分が付着し、その付着量が粒子ごとに異なるため、密度や吸水率が変動してしまいます。
また、貯蔵や運搬の管理状態が悪ければ、不純物が混入し、さらなる品質低下を引き起こす可能性もあります。
高品質な再生骨材コンクリートを製造するためには、まず高品質な再生骨材の製造技術が求められますし、私たち発注者、設計者、施工者といった全ての関係者が、再生骨材の等級と使用すべき構造物を十分に考慮し、理解を深めていくことが重要になってきます。
2. コスト面の課題
そして、もう一つがコストの問題です。これが再生骨材の普及における最も大きな壁となっています。
高品質な再生骨材を取り出そうとすると、その製造過程で粉体分(セメント水和物の粉や骨材の粉体)が大量に発生します。現状、これらの副産物の有効利用が進んでおらず、処分に多額の費用がかかり、ストック場所の確保にも苦労しているのが現実です。
結果として、コストを抑えるために、解体コンクリート塊の流通は、排出場所と使用場所が近く、破砕コストが低い路盤材などへの利用が促進されてしまうことになるわけです。
【今後の展望】私たちが取り組むべきこと
私たちは、「環境を破壊せず、資源を使いすぎない」という持続可能な社会の実現のために、再生骨材の利用を諦めるわけにはいきません。
コンクリート主任技士として、この課題にどう貢献していくか、私なりの考えを述べさせていただきます。
1. 技術革新と副産物利用の徹底
まず、高品質な再生骨材を低コストで製造するための技術革新が不可欠です。特に、再生骨材に付着しているセメント水和分の除去技術や、製造コストの低減は大きな課題です。
そして、製造時に発生する微粉分を「二次廃材」とせず、例えば歩道舗装用のコンクリートブロック製造に利用するなど、有効利用を図ることが必要です。副産物利用には技術的な弊害を伴うことも多いですが、継続的な技術開発で対応していく必要があります。
2. 品質基準の整備とライフサイクルコストの考慮
再生骨材の普及に向けた重要な方策として、品質や利用用途についての基準の整備が急務だと考えます。
また、コストが壁となることが多い現状ですが、再生骨材を使用することで、長期的に天然資源の採掘抑制や廃棄物処理費の削減など、ライフサイクルコスト(LCC)全体で低減を図れる可能性があります。今後は、ライフサイクル全体を考慮した経済性を評価し、コスト低減を図る必要があります。
3. 業界全体での理解と供給システムの確立
再生骨材は、私たちの業務(生コンプラントや現場施工)においても、今後、活用が必須となっていくでしょう。
高品質な再生骨材の製造は、原料となる解体コンクリートの分別や処理、そして最終的な供給まで、一貫したシステムの確立が必要です。私たちは、単に目の前の材料として扱うだけでなく、リサイクル全体を視野に入れたシステム作りに参画していく必要があります。
コンクリート構造物のライフサイクル全体を考慮する時代において、再生骨材をいかに有効活用し、天然骨材の枯渇問題への対応や環境負荷の低減を図っていくか、これは私たちコンクリートのプロフェッショナル全員に課せられた使命です。
これからも、再生骨材の最新の実施報告等の情報収集を行い、自己研鑽に努めていきたいと強く思います。
皆さんもぜひ、日々の業務の中で再生骨材の可能性について考えてみてくださいね!

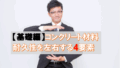
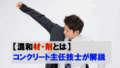
コメント